マルセイユ石鹸の歴史がわかる3分40秒の動画を紹介します。
タイトルは、Naissance savon de marseille(マルセイユ石鹸の誕生)
マルセイユ石鹸は、フランス南部の港町マルセイユで14世紀から作られてきた、伝統的な植物性石鹸です。
私はマルセイユ石鹸
マルセイユ石鹸自身が自分の出自を語る内容です。
3分43秒。
Savon de marseille:トランスクリプション
Je suis né il y a très longtemps, sans doute au Moyen-Orient. Personne ne sait vraiment comment je suis venu au monde. Ce que je sais, c’est que les Phéniciens, puis les Gaulois, utilisaient déjà enfin une de mes formes rudimentaires, composée de graisses animales et de cendres.
Pendant longtemps, j’ai été fabriqué de façon aléatoire, sans véritable charte de fabrication. J’étais un produit rare, encore peu connu.
Et puis, au Moyen Âge, j’ai rencontré Marseille… ou c’est plutôt elle qui m’a adopté. Elle a su voir mon potentiel et m’a dédié des usines entières, aidée en cela par la proximité des matières premières dont j’avais besoin pour être fabriqué : l’huile d’olive de Provence, le sel et la soude de Camargue. Et même le mistral qu’on utilisait pour me sécher par les fenêtres ouvertes des savonneries.
Marseille et sa région ont mis au point un véritable procédé des techniques et des savoir-faire : tout un procédé de fabrication. C’est à partir de là que j’ai commencé à être distribué un peu partout en France, et par bateau dans le bassin méditerranéen, et puis dans le monde entier.
Marseille et moi sommes devenus indissociables. C’est notre union qui m’a véritablement permis d’atteindre ma qualité et ma renommée. C’est pour cela — parce que je ne suis rien sans elle — que j’ai pris son nom et que je m’appelle Savon de Marseille.
Dès 1688, un édit de Louis XIV, dit l’édit de Colbert, acte notre alliance et réglementé ma fabrication. Ces règles — l’utilisation d’huile d’olive, la proscription de graisses animales, et la cuisson en chaudron — ont d’ailleurs peu changé depuis.
Pourtant, mon histoire n’est pas si simple. D’abord, il y a eu l’apparition des lessives dans les années 60, ensuite la concurrence internationale. Mon nom, si connu et emblématique, n’a jamais été protégé.
En gros, on peut appeler “Savon de Marseille” n’importe quel savon, fabriqué n’importe où sur le globe, et composé de n’importe quoi. Et depuis trop longtemps, j’ai vu apparaître des usurpateurs qui utilisent mon nom, mais qui sont loin d’avoir mon pedigree — à savoir la qualité de ma composition et mon origine géographique.
Toutes ces circonstances ont été désastreuses pour moi. Et le nombre d’usines de savon qui me produisaient à Marseille et dans sa région a fondu comme neige au soleil.
Moi, j’ai toujours été ouvert et généreux. J’appartiens à celui qui me fait, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs — à la seule condition que je sois fabriqué à Marseille ou sa région, dans le respect de la charte de fabrication qui a fait ma réputation.
Aujourd’hui, nous avons décidé de ne pas rester les bras croisés. Nous avons sollicité l’État pour obtenir un label IGP — une Indication Géographique Protégée — pour que mes consommateurs puissent m’identifier en tant que le véritable Savon de Marseille.
Car pour l’instant pour eux c’est compliqué de reconnaître le vrai du faux. Or moi, je n’ai rien à voir avec ceux qui me copient. Je suis l’initiale, l’original, le légitime.
Mes vertus sont reconnues depuis toujours dans le monde entier. Je suis l’un des derniers produits cosmétiques fabriqués en France de manière traditionnelle depuis le Moyen Âge. Je mobilise encore aujourd’hui les mêmes savoir-faire ancestraux.
Comme tant d’autres produits, j’aurais pu — j’aurais dû — disparaître face à l’usure du temps, des modes et des difficultés économiques. Et pourtant, je suis toujours là.
J’ai fait mes preuves et traversé les siècles, car je suis un produit de qualité aux vertus multiples. Je suis un morceau vivant de notre histoire culturelle et industrielle, un fragment de notre patrimoine collectif. Je suis un dinosaure vivant… mais fragile.
*自動生成のトランスクリプションを参考にして作っているので間違えている可能性があります*
マルセイユ石鹸:和訳
私はすごく昔、中東あたりで生まれました。どうやってこの世に現れたのか、実は誰も正確には知りません。わかっているのは、フェニキア人、そしてガリア人が、すでに私の原型のようなもの――動物の脂と灰でできたもの――を使っていたということです。
長い間、私は適当な方法で作られ、本格的な製造基準もありませんでした。私は希少で、まだあまり知られていない存在だったのです。
そして中世に、私はマルセイユに出会います…いや、むしろマルセイユが私を迎え入れてくれました。マルセイユは私の可能性を見抜き、私のための工場を丸ごと用意してくれました。それができたのは、プロヴァンスのオリーブオイル、カマルグの塩とソーダなど、私の製造に必要な原材料がすぐそばにあったからです。私を乾かすのに使うミストラル(地方の風)まで、石鹸工場の窓を開けて用意してくれました。
マルセイユとその地域は、技術と職人の知識を結集し、本物の製造工程を確立しました。ここから私はフランス各地に、さらに船で地中海沿岸、そして世界中にまで広がっていったのです。
マルセイユと私は切っても切れない関係になりました。この結びつきこそが、私に品質と名声をもたらしたのです。だから――私はマルセイユなしでは何者でもない――彼女の名を冠して「サヴォン・ド・マルセイユ」と名乗るようになりました。
1688年には、ルイ14世による「コルベール勅令」が私たちの結びつきを正式に認め、私の製造を規定しました。オリーブオイルの使用、動物性脂肪の禁止、釜炊きによる製造などが定められました。これらは今でもほとんど変わっていません。
けれども、私の歴史はそう簡単なものではありません。1960年代に洗濯用洗剤が登場し、その後は海外との競争があります。私の名は有名で象徴的でしたが、(法的な)保護は一度もされませんでした。
つまり、「サヴォン・ド・マルセイユ」と名乗ることは、どんな石鹸でも、世界のどこで作られてもできてしまうのです。どんな成分で作られていても。
長い間、私は、私の名前を使いながら、まったく別物である石鹸たちが登場するのを見てきました。彼らには、私が持つ品質や地理的な背景はありません。
こうした状況は、私にとって壊滅的でした。マルセイユやその周辺で私を作っていた工場の数は、雪が日差しで溶けるように減っていきました。
それでも私は、いつもオープンで寛容でした。地元であれ他所であれ、誰が私を作ってもかまいません―マルセイユまたはその周辺で、伝統的な製造基準にのっとって作られ、私の評判を落とさない限りは。
私たちはもう黙って見ているのはやめました。国に対し、「IGP(地理的表示保護)」の認定を求めるよう申し立てました。消費者が本物のサヴォン・ド・マルセイユを見分けられるようにするためです。
というのも、今、消費者が本物と偽物を見分けるのはとても難しいのです。でも私は、コピー品とはまったく違います。私は最初の存在で、オリジナルで、正統です。
私の効能は、古くから世界中で知られてきました。私は中世から続く伝統的製法で、今もなおフランスで作られている、最後の化粧品のひとつです。今日でも、職人たちは昔ながらの技術を使って私を作っています。
たくさんの他の製品が、時代の流れ、流行、経済的困難の中で姿を消すのを見てきました。私もそうなりそうでした。それでも私はずっと存在しています。
「私はその実力を証明し、何世紀にもわたって生き延びてきました。なぜなら、私は多くの効能を持つ高品質な製品だからです。私は、私たちの文化的・産業的歴史を生きて伝える存在で、人々の共有財産の一部です。私は生きている恐竜、だけど壊れやすいのです。
単語メモ
sans doute(副) たぶん、おそらく
rudimentaire(形) 原始的な、簡素な
graisse(f) 脂肪、脂(例:graisses animales=動物性脂肪)
aléatoire(形) 不確定な、でたらめな
matière première(f) 原材料、原料となる資源
soude(f) ソーダ、苛性ソーダ(石鹸の製造に使う)
savoir-faire(m) 職人技、熟練の技術
indissociable(形) 切っても切れない、不可分な
renommée(f) 評判、名声
édit(m) 勅令、布告(例:l’édit de Colbert)
acter(v) 公式に記録する、明文化する
proscription(f) 禁止、排除(例:la proscription des graisses animales)
usurpateur(m) 名前をかたる者、偽物
désastreux / désastreuse(形) 壊滅的な、悲惨な
appartenir à(v) ~に属する、~のものである
charte(f) 憲章、基準書(charte de fabrication=製造基準)
rester les bras croisés(熟) 腕を組んだまま=何もしないでいる
solliciter(v) 要請する、申請する
n’avoir rien à voir avec A(表現) Aとはまったく関係がない
initial(e)(形) 最初の、元祖の
vertu(f) 効能、美徳(例:mes vertus=私の効能)
mobiliser(v) 動員する、活用する(職人技などを)
usure du temps(f) 時の経過による劣化・風化
固有名詞メモ
Marseille(地名) マルセイユ。南フランスの港町で、サヴォン・ド・マルセイユの産地。
Camargue(地名) カマルグ。塩やソーダの産地として知られる、マルセイユ近郊の地域。
Provence(地名) プロヴァンス。オリーブオイルの産地として登場。南仏の代表的な地方。
le mistral(名詞・m) ミストラル。プロヴァンス地方に吹く強風で、石鹸を乾燥させるのに使われた。
l’édit de Colbert(名詞句) コルベールの勅令。1688年、ルイ14世の下で制定された石鹸の製造規定。
Louis XIV(人名) ルイ14世。「太陽王」と呼ばれるフランス王。サヴォン・ド・マルセイユの品質規定に関与。
Colbert(人名) コルベール。ルイ14世の財務総監。勅令を通じて石鹸製造の基準を定めた。
IGP(Indication Géographique Protégée) 地理的表示保護制度。特定の地域で作られた製品であることを保証する認証制度。
le bassin méditerranéen(名詞句) 地中海沿岸地域。サヴォン・ド・マルセイユの輸出先として登場。
きょうのプチ文法:à condition que + 接続法
「~という条件で」と言いたいときによく使われる表現。queのあとは、接続法(subjonctif)が来ます。
■ 例文(Savon de Marseille の語りから)
À la seule condition que je sois fabriqué à Marseille ou sa région…
(マルセイユまたはその周辺で製造されているという条件でのみ。)
être の接続法現在形 sois が使われています。
■ ほかの例文
・Je te prête ce livre à condition que tu me le rendes demain.
(明日返してくれるという条件で、この本を貸すよ)
・Vous pouvez entrer à condition que vous soyez silencieux.
(静かにするという条件で、入っていいですよ)
■ 接続法が必要な理由
à condition que は、「話し手の意志・制限・条件」を表す表現で、確実な事実ではなく、未確定の行為や状態を表すので接続法が続きます。
■ 類似の条件表現(いずれも接続法)
pourvu que(〜でさえあれば)
à moins que(〜でない限り)
à supposer que(〜だと仮定して)
en supposant que(〜だと仮定すれば)
本物のマルセイユ石鹸の見分け方
本物のマルセイユ石鹸を見分ける方法を説明している2分半の動画です。
Comment reconnaître un Vrai Savon de Marseille (どうやって本物のマルセイユ石鹸と見極めるか)
2分38秒。
動画で説明されていた見分け方をまとめます:
1.形と刻印
・形は立方体や直方体などシンプル。
・表面には「72%」などの油分(植物油)含有率、重量(100g〜1kg)、製造会社名、または「マルセイユ石けん職人組合(UPSM)」のロゴが刻印されています。
2.色
・緑色:オリーブオイル使用
・白〜ベージュ:ココナツ(コプラ)油やパーム油使用
・ピンク、赤、ターコイズ、虹色などのカラフルな石けんは偽物です。
3.香り
香料は無添加。独特のオリーブオイルの香りがします。
4.成分表示
・成分はとてもシンプルで、5〜6種類程度。
例:オリーブ油、パーム油、ココナツ油(コプラ油)、水、塩、苛性ソーダ(ソーダ灰)。
・動物性脂肪(sodium tallowate)や保存料、香料、着色料などが入っているものは本物ではありません。
マルセイユ石鹸(Savon de Marseille)は政府にIGP認定を要請しましたが、現時点ではまだ認定されていません。
◆関連記事もどうぞ
*****
オリーブオイル70%以上入っていて、手作業で作っているマルセイユ石鹸ですが、手に入りやすい材料を使っているので、値段はそこまで高くありません。
調べたところ、フランス現地でなら、
100gキューブ:2〜3ユーロ程度(1ユーロ、170円とすると、約340〜510円)
300g〜600gブロック:5〜8ユーロ程度(約850〜1,360円)
日本だと輸入品だから高くなります。特に今は円安なので尚更ですね。











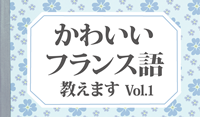

この記事へのコメントはありません。