春の訪れとともにやってくる、キリスト教の祝祭、Pâques(イースター)。2025年は今週がイースターの週末です。
フランスではこの時期、チョコレートの卵やウサギをあちこちで見かけますが、そもそもなぜ卵?なぜウサギ?と思ったことはありませんか?
今回紹介するのは、そんな素朴な疑問に答えてくれる約2分のフランス語の動画です。
タイトルは、Pourquoi mange-t-on des lapins de Pâques ? (なぜイースターにうさぎを食べるのか?)
キリスト教の復活祭の話だけでなく、野ウサギの繁殖力、ゲルマン神話の女神、ドイツの伝説、オーストラリアのビルビーにまで話が広がり、楽しみながら語彙と文化が学べると思います。
Pourquoi mange-t-on des lapins de Pâques ?
2分
トランスクリプション
La fête de Pâques célèbre la résurrection du Christ. C’est pour cela que l’on mange des œufs en chocolat, symbole de fécondité et de renouveau, qui évoque la renaissance du Christ. Mais alors, pourquoi mange-t-on aussi des lapins en chocolat et pas, par exemple, autre chose ?
Alors, il y a trois théories. La première, c’est que le lapin de Pâques est un héritage du haut Moyen Âge, et en particulier d’une divinité germanique d’alors, Éostre, liée au printemps et à la fertilité. Or, l’animal emblématique d’Éostre, c’était le lièvre. Sans doute parce que l’on avait déjà remarqué alors que le lièvre, qui est une sorte de grand lapin, était un animal particulièrement fertile.
La femelle du lièvre, la hase, peut être fécondée une seconde fois, alors qu’elle est déjà enceinte, et produire jusqu’à 15 petits par an. D’où lièvre égale fertilité égale le renouveau du printemps égale Éostre. Et comme Pâques, on l’a dit, c’est la renaissance du Christ, moment de renouveau, il est possible que le symbole païen d’Éostre ait peu à peu migré dans le christianisme.
L’autre théorie tient plus de la légende. Au XVIIe siècle en Allemagne, la tradition de cacher des œufs à Pâques existait déjà. Et deux enfants qui avaient aperçu un lapin auraient cru que les œufs de Pâques cachés par leur mère avaient été apportés par l’animal. D’où lapin égale Pâques.
Et puis au Moyen Âge, sans qu’on sache vraiment pourquoi, les gens ont commencé à peindre sur les œufs de Pâques un motif de trois lièvres entrelacés dans un cercle. En allemand, on appelle ce motif le Dreihasenbild. Le quoi ? Le Dreihasenbild. Et petit à petit, le lapin serait ainsi devenu un symbole de Pâques.
Pour finir, une anecdote : en Australie, où le lapin trop prolifique est considéré comme nuisible, on lui préfère depuis un autre animal, le Bilby. Le Bilby est une sorte de lapin “raté” avec un nez beaucoup trop pointu. Mais surtout, il est en voie de disparition. Et du coup, l’Australie se sert de Pâques pour attirer l’attention sur sa condition et lever des fonds.
なぜイースターにウサギを食べるの?
イースターの祭りは、キリストの復活を祝うものです。
そのため、チョコレートの卵を食べます。これは多産と再生の象徴であり、キリストの復活を想起させます。
でも、それならなぜチョコレートのウサギも食べるのでしょう? たとえば他のものではなく?
それについては、3つの説があります。
1つ目は、イースターのウサギは初期中世の遺産だという説です。
とくに、当時のゲルマンの女神、エオストレに由来するとされます。彼女は春と多産に関連づけられた存在です。
さて、そのエオストレの象徴的な動物が、野ウサギでした。
おそらくその理由は、当時すでに野ウサギが、一種の大きなウサギであり、特に繁殖力の高い動物だと気づかれていたからです。
野ウサギのメス、すなわちハーズは、妊娠中にもう一度受精することができます。
つまりすでに妊娠している状態でです。
そして年に最大15匹の子を産むこともあります。
そこから、野ウサギ=多産=春の再生=エオストレ、というつながりになります。
そしてイースターが、すでに述べたように、キリストの復活=再生の瞬間であることから、エオストレの異教的なシンボルが、徐々にキリスト教に取り入れられていった可能性があります。
もう一つの説は、むしろ伝説に近いものです。
17世紀のドイツでは、すでにイースターに卵を隠す習慣がありました。
そして、1匹のウサギを見かけた2人の子どもが、母親が隠したイースターの卵を、そのウサギが運んできたと思い込んだそうです。
そこから「ウサギ=イースター」という図式が生まれました。
それから中世には、はっきりとした理由は分かっていないものの、人々はイースターエッグに、輪の中に絡み合った3匹のウサギの模様を描き始めました。
ドイツ語では、この模様を「ドライハーゼンビルト」と呼びます。
なに? ドライハーゼンビルトです。
そして少しずつ、ウサギがイースターの象徴になっていったというわけです。
最後にひとつちょっとしたエピソードを。
オーストラリアでは、ウサギが繁殖しすぎて害獣と見なされており、代わりに、別の動物「ビルビー」が好まれるようになりました。
ビルビーは、鼻がやたらと尖った「失敗作のウサギ」といった感じの動物です。
でも、何よりも絶滅の危機にあります。
そのためオーストラリアではイースターを利用して、この動物の状況に注目を集め、資金を集めようとしているのです。
単語メモ
fécondité(f) 多産、繁殖力
symbole de fécondité 多産の象徴
renouveau(m) 再生、復活、新たな始まり
le renouveau du printemps 春の再生
lièvre(m) 野ウサギ(lapin より大きく、耳が長い)
l’animal emblématique d’Éostre, c’était le lièvre エオストレの象徴的な動物は野ウサギだった
païen(adj / n) 異教の、異教徒の
le symbole païen d’Éostre エオストレの異教のシンボル
aurait cru(v, conditionnel passé) 信じたらしい、思い込んだようだ
Ils auraient cru que les œufs venaient du lapin 彼らはその卵がウサギのものだと信じたようだ
motif(m) 模様、図柄
un motif de trois lièvres entrelacés 絡み合った3匹のウサギの模様
lever des fonds(v) 資金を集める
lever des fonds pour protéger le bilby ビルビーを守るために資金を集める
きょうのプチ文法:条件法過去(conditionnel passé)
イースターのウサギの伝説を語るなかで、こんな文が登場しました。
Deux enfants auraient cru que les œufs avaient été apportés par l’animal.
(2人の子どもは、その卵をウサギが持ってきたと信じたようです)
ここで使われている auraient cru は、条件法過去という時制です。
✔ 条件法過去とは?
過去のことについて「〜したはず」「〜したらしい」「〜したかもしれない」といった伝聞や推測、仮定の表現に使います。
✔ 作り方
avoir(または être の)条件法現在 + 過去分詞
例:
– ils auraient cru(彼らは信じたようだ)
– il aurait dit(彼は言ったらしい)
– on aurait vu(見たかもしれない)
✔ よく使う場面
・伝説や昔話を語るとき
・ニュースの伝聞情報 ex. Le voleur aurait fui par la fenêtre. その泥棒は窓から逃げたかもしれない。
・「〜すべきだった」「〜しなければよかった」など、後悔を表すとき ex. J’aurais dû étudier.=勉強すべきだった、Je n’aurais pas dû dire ça. そんなこと言わなければよかった
関連動画・イースターのチョコレートを安く買う
こちらは数日前にアップされた2分のニュースクリップです。
タイトルは、Chocolat : les bonnes affaires à la veille de Pâques(チョコレート:イースター前夜の掘り出し物)
カカオが高騰し、チョコレートが高いので、お得にチョコレートを買おうとする消費者の様子が紹介されています。
動画では、ネット通販でイースター用のチョコレートをまとめ買いする様子が紹介されます。
登場する父子は、割引価格でたくさんのチョコレート(卵やウサギ型など)を手に入れたことに満足しています。
購入先はディスカウント系の通販サイトで、市販価格より20〜30%安いとのこと。実際に30ユーロほど節約できました。
背景にあるのは、カカオの価格高騰です。1年間で14%も上昇しており、多くの人が少しでも安くチョコを買おうと、プロモーションや全額キャッシュバックのような特典を探しています。
さらに、カカオを一切使わないフェイクチョコレートも登場しました。ブドウの種やひまわりの種から作られ、価格は本物より20%安いそうです。見た目は本物そっくりですが、香りで違いがわかるとか。
イースター関連記事もどうぞ
イースター(復活祭)に卵を使う風習はどのようにして生まれたのか?(1分で説明)
******
私も子供が小さい時は、イースターにお菓子を焼いたりしましたけど今は特に何もしません。
やはりキリスト教のお祝いなので日本人の私にはそんなにピンと来ないからです。
でも、この時期売り場はとってもカラフルになり、長い冬が終わってようやく春が来たと感じられるので嫌いなイベントではありません。











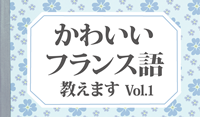

この記事へのコメントはありません。