食品ロスを減らすためにフランスのある中学校が取り入れた方法をルポしている2分の動画を紹介します。
タイトルは、Avec l’assiette unique, fini le gaspillage alimentaire à la cantine(一皿方式で、給食の食品ロスに終止符)。
食品を1枚の皿に全部盛るというシンプルなやり方に変えただけで、廃棄してしまう食べ物がかなり減ったと伝えています。
Finir le gaspillage alimentaire
2分9秒。フランスの字幕あり。
リポーターもやり方を説明する人もこの学校の生徒だと思います。ほほえましい動画ですね。
トランスクリプション
Et si c’était la fin du gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires ? Un défi qui semble compliqué à relever, mais pas impossible. La preuve en est ici, au collège Ernest Schaffner de Roost-Warendin, où l’assiette unique a été mise en place.
Alors Louis, comment ça marche ?
Eh bien, après avoir déposé le plateau à table, on prend une assiette, compartimentée ou pas, selon nos envies. Après, on vient se servir en entrée.
Et pour le plat, comment ça marche ?
Donc le plat, on peut le mettre dans les autres compartiments. Au moins, ça ne se mélange pas.
Et si je veux me resservir ?
Eh bien, on doit d’abord finir ce qu’on a mangé, puis on peut se resservir, pour éviter tout le gaspillage.
Avant, on jetait beaucoup. Maintenant, l’assiette unique encourage la consommation raisonnée.
Alors, quel est le bilan de ce nouveau mode de fonctionnement ?
Le premier, c’est d’avoir réussi à associer l’assiette unique avec le self participatif. Donc, le self participatif, dans un premier temps, a permis à l’élève de se servir seul. Ensuite, l’assiette unique est venue s’ajouter dessus. Et là, il sert à moi à réduire les déchets, et à eux de se rendre compte de ce qu’ils peuvent mettre dans une assiette.
Et en termes de chiffres, est-ce que vous avez vu une différence entre l’avant et l’après ?
Avant, c’était 30 à 40 kilos par jour. Aujourd’hui, on en jette 5 à 10 kilos, tout compris.
Super !
Oui donc franchement, c’est top. C’est l’argent économisé qui permet de réinvestir dans l’approvisionnement local, dans des aliments labellisés, et de faire plaisir encore plus aux enfants, finalement.
C’est déjà un premier bilan très concluant. Alors, quels sont les avantages de ce self pour les chefs du département ?
Au niveau des gens qui y travaillent, le mode de fonctionnement a changé pour ces personnes-là. Donc, moins de gestes répétitifs, et ils interviennent davantage en termes de conseil, de manière à s’assurer qu’il y a un équilibre au niveau nutritionnel qui soit respecté.
Les assiettes n’ont jamais été aussi vides. Ici, avec l’assiette unique, on se régale, tout en réduisant le gaspillage alimentaire.
食品ロスを減らす・和訳
学校給食で食品ロスがなくなる日が来るとしたらどうでしょう?
一見むずかしそうな課題ですが、不可能ではありません。
その証拠がここ、ルースト=ヴァランダンのエルネスト・シャフナー中学校です。この学校では、「一皿方式」が導入されました。
ルイ、どうやってやるの?
えっと、まずテーブルにトレイを置いて、それから好きなタイプの皿を、好みで仕切りのあるものかないものを取ります。
それから前菜を取りに行きます。
メインディッシュはどうするの?
メインは、他の仕切りに入れればいいんです。そうすれば混ざらずにすみます。
おかわりしたい時は?
まずは自分の皿を食べ終わらないといけません。それからおかわりをします。そうやってロスを防ぎます。
以前はたくさん捨てていましたが、今はこの「一皿方式」で、食べる量を考えて選ぶようになりました。
この新しいやり方の成果はどうですか?
まず第一に、一皿方式とセルフサービスの組み合わせが成功しました。
最初に導入したのが「参加型セルフ」。これで生徒が自分でよそえるようになったんです。
そのあとに「一皿方式」を追加しました。
私たちはゴミを減らせるし、生徒は自分がどれくらい盛ったらいいのか把握できるようになりました。
数字で見ると、以前と導入後とでは違いがありましたか?
以前は、1日30〜40キロの食品廃棄が出ていました。今は、全部で5〜10キロに減っています。
すごいわ。
はい、本当に素晴らしいです。
節約できたお金は、地元食材の調達や、ラベル付きの品質認証食品に再投資できるようになりました。その結果、子どもたちもより満足して食事ができるんです。
すでに非常に満足のいく最初の結果が出ていますね。このシステム、県の調理師たちにとってはどんなメリットがあるのでしょうか?
スタッフの働き方も変わりました。繰り返し作業が減り、そのぶんアドバイスなどに時間を使えるようになりました。ちゃんと栄養バランスがとれるようにといったことです。
お皿は、かつてないほど空っぽになっています。
この学校では「一皿方式」で、おいしく食べて、食品ロスを削減しています。
単語メモ
relever(v) (困難・挑戦などに)立ち向かう、受けて立つ
Un défi qui semble compliqué à relever.
立ち向かうのが難しそうな挑戦。
compartimenté / compartimentée(adj) 仕切られた
On prend une assiette, compartimentée ou pas…
仕切りのあるお皿(またはないもの)を取ります。
bilan(m) 成果、結果、総括
Quel est le bilan de ce nouveau mode de fonctionnement ?
この新しいやり方の成果はどうですか?
associer A à B(v) AとBを結びつける、組み合わせる
Associer l’assiette unique avec le self participatif.
一皿方式とセルフサービス方式を組み合わせる。
approvisionnement local(m) 地元からの供給、地産地消
L’argent économisé permet de réinvestir dans l’approvisionnement local.
節約されたお金で地元からの仕入れに再投資できる。
concluant / concluante(adj) 納得のいく、満足のいく、説得力のある
C’est un premier bilan très concluant.
非常に満足のいく第一の成果。
gaspillage alimentaire(m) 食品ロス
C’est la fin du gaspillage alimentaire ?
食品ロスは終わるのか?
se servir(v) 自分で取る、取り分ける
L’élève peut se servir seul.
生徒が自分で取れるようになる。
self participatif(m) セルフサービス方式
Le self participatif permet à l’élève de se servir.
セルフサービスで生徒が自分で盛る。
équilibre nutritionnel(m) 栄養バランス
S’assurer qu’il y a un équilibre nutritionnel.
栄養バランスがとれているかを確認する。
今日のプチ文法:仮定の話をするときの si + 半過去
「もし~だったら?」「~だったとしたら?」という仮定の表現には、si + 半過去形(imparfait) がよく使われます。
フランス語では、現実とは違う状況や起こる可能性が低いことを想像するとき、こんな言い方をします:
Et si c’était la fin du gaspillage alimentaire ? 食品ロスが終わるとしたら?
文法的には、si + 半過去形の仮定を表す節のあと、条件法現在の主節がくるのが基本ですが、この文では主節が省略されています。
◆例文
Si j’avais le temps, je voyagerais plus. もし時間があれば、もっと旅行するのに。
Si tu étudiais un peu plus, tu comprendrais. もう少し勉強すれば、わかるようになるよ。
◆主節を省略して「Et si ~ ?」だけで話しかけることもよくあります。
Et si on sortait ce soir ? 今夜出かけない?(=出かけるのはどう?)
Et si tu changeais de travail ? 転職してみたら?
食品ロス・関連動画
Le gaspillage alimentaire expliqué aux enfants(子ども向けの食品ロスの説明)
2分21秒
とてもわかりやすく行動に移しやすいアニメーション動画です。
内容の簡単なまとめ:
◆食品ロスってなに?
世界では、1人あたり年間20kgもの食べ物が捨てられており、そのうち7kgは未開封のまま。 特に無駄になっているのは:
食べ残し(24%)
腐った野菜や果物(24%)
開封済みの商品(20%)
料理(18%)
パン(14%)
結果的に、地球上で生産された食べ物の3分の1がゴミになっています。
◆食品ロスはどこで起きてる?
農場、輸送中、倉庫、加工工場、スーパーなど、食品の流通のあらゆる段階で無駄が出ています。
◆家でできる対策は?
買いすぎないために、買い物の前に:
・1週間分の献立を考えてリストを作る
・キッチンの在庫をチェックする
・賞味期限の種類を理解することも大切:
DLC(消費期限)=過ぎたら食べちゃだめ
DDM(品質保持期限)=味は落ちるけど食べられる
・買い物での注意
- 必要な分だけ買う
- 量り売りを利用する
- 見た目が悪くても美味しい野菜や果物を選ぶ
◆家で気をつけること
・冷蔵庫を整理して適切な温度を保つ
・先に傷みそうなものから食べる
・残り物は工夫して食べるか冷凍する
◆給食でできること
・自分の食欲に合わせて取る
・食べきれないならパンを取らない
◆おぼえておきたい4つの「もったいない」対策:
1.必要な分だけ取ろう
2.賞味期限をよく見よう
3.見た目の悪い野菜・果物も食べよう
4.残り物は料理し直そう!
一皿方式のメリット
最初に紹介した動画に出てきた中学校では、1つの皿に盛り付けるというものすごく単純な方法で、かなりの量の食品の廃棄を減らしました。ワンプレートルールはシンプルですが、以下の効果を期待できます。
・自分で量を調整できる⇒食べられる分だけを盛る
・おかわりOKのルール
食べ終わったらおかわりできるシステムがあるため、最初にたくさん取って、結局残すことがなくなります。
・視覚的な管理がしやすい
すべてが一皿にのっているので、食べ残しがよくわかる。先生やスタッフが「ちょっと多すぎるかも」と助言できる。
・責任感と自立心を育てる
「自分で選ぶ→残さない」という流れができ、子どもたちに自分の食べ物に責任を持つ感覚が育つ。
・片付けや廃棄が楽になり、意識が高まる
食べ終わった後に残ったものが一皿に集中するため、残量がわかりやすく、「もったいない」が可視化される。
■関連記事もどうぞ
フランスの学校食堂 La cantine(カンティーヌ):子どもたちの本音は?
*****
久しぶりに食品の廃棄に関する動画を紹介しました。
私も食品の無駄が出ないように買いすぎないようにしています。私は地球のためというよりも自分の節約のためですが、色々やってみて分かったことは結局買いすぎると無駄になるということです。
今日紹介した動画が皆さんの参考になれば幸いです。



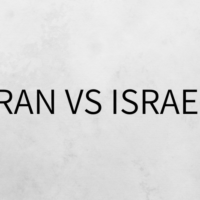




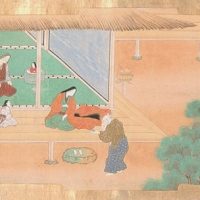


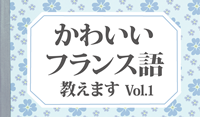

この記事へのコメントはありません。