ほかの受講生さんはとっくに終わっている翻訳講座第11回、前半の受講メモです。
8回~10回までは復習回でしたが、11,12回は同じ課題の解説です。課題は水林章先生の「メロディ ある情念の系譜(Mélodie, chronique d’une passion)」という本の一節です。今回はこの本の著者についてご紹介します。
きょうのメニュー
・水林章
・文体の複雑さは深い思考を表している。
水林章
「水林先生」と先生と書いてしまってますが、解説してる先生が先生と呼んでいるからです。
水林先生(1952~)は17-19世紀のフランス文学、フランス思想の研究が専門の学者で、上智大学の教授(いまも教えているのかどうかは知りません)。
日本人なのですが、達意のフランス語で本を書いていて、文学的なテキストの一例として、先生が選んだ翻訳課題です。
これは小説ではなく自伝的エッセイです。日本語でエッセイというと軽い読み物が多いのですが、文学的でところどころ研究書っぽい記述もあって難しいです(少なくとも私には)。「随想録」と呼んだほうがいいかもしれませんね。
ご自身の著書が2冊ありまして、新しいほうが「メロディ」です。
この本
Amazonへ⇒Melodie
メロディは著者の今は亡き愛犬です。
これはご本人がフランス語で著書について語っている動画です。11分と長いですけどよろしければごらん下さい。
亡くなったお父さんのことを話されていますね。彼にとってお父さんの存在は大きいようです。
というのも、お父さんは自分自信が苦学生だったせいか、息子のやりたいことはなんでも応援してくれる人だったのです。
お父さんは、水林先生が18歳のとき、ラジオ講座でフランス語を始めたところ、すごく高価なオープンリールデッキ(録音する機械)を買ってくれました。
彼はそれを使って一日中、フランス語をしゃべる練習をしていたそうです。
そのあたりのことは、この「他言」という本に書いてあります。
Amazonへ⇒Une langue venue d’ailleurs
この本は私も買って、途中まで読みました。最初のほうはまだ読めたのですが、学術的な記述が多くなると、とたんに難しくなって、モンペリエに旅立つあたりのところで止まっています。辞書を使えば読めるかもしれませんけど。
詳しくはFC2ブログに書いているので、興味のある方はごらんください。教養人の著書らしく、モーツアルトの音楽やほかの文学書への言及があります。
⇒«UNE LANGUE VENUE D'AILLEURS»~水林章
⇒鏡に向かって名前を連呼するアントワーヌ・ドワネル
文体の複雑さは深い思考を表している
格調高い文章
さて、今回の講義の冒頭にでてきた生徒の質問、「水林先生のは格調高すぎるが、もう少し平易に書くことはできないのでしょうか?」
これ、私の書いた質問です^^;ただ、ちょっと言葉が違います。私の質問は、「水林先生のフランス語は格調が高すぎる気がします。もう少し、シンプルに書くという手はないのでしょうか?それともこれがふつうのフランス語なのでしょうか?」です。
これに対しての答えは
もちろん平易に書くことはできるが、そんなことをするのはありえない。文体を練ることがフランスのインテリの文化であり、文体が複雑である、ということは深い思考ができることの証なのである。
とのことでした。
そういえば、達人講座ののミーティングでも、フランス語の特徴として、文体の複雑さがあげられていました。
文は人なり
フランス文化に「文体は人なり」という伝統があるそうです。
これは博物学者のビュフォン(1707-1788)という人がフランス科学アカデミーというところの会員になったとき、演説で「文体論(Discours sur le style)」というのを披露したとき、ビュフォンは Le style c’est l’homme même と言いました。
おそらく、この考え方が、フランスの深い思索を表すためにこった文体を用いるようになった源泉なのではないか、ということでした。
ビュフォンは科学者でしたが、文才があったのですね。「博物誌」という本を残しています。
確かに言語化できないと、思索も深まりませんが、「じゃあ、ほかの人が読んだときどうなんだ」、という問題もあります。
日本の京都学派という哲学の学派では、「頭のいい人は、どんな人にも説明できるものである、つまり文体は平易なはず」という考え方があるそうです。思考の深さと文体は関係がないということです。
一言で文体と言ってもいろいろありますけどね。
私は、シンプルな文体が好きなのですが、フランス語を学習する以上、こった文章を読む練習も必要ですね。
それでは、次回の翻訳講座の記事をお楽しみに。








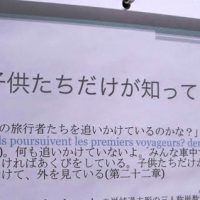




この記事へのコメントはありません。